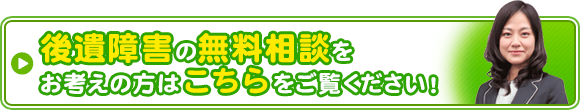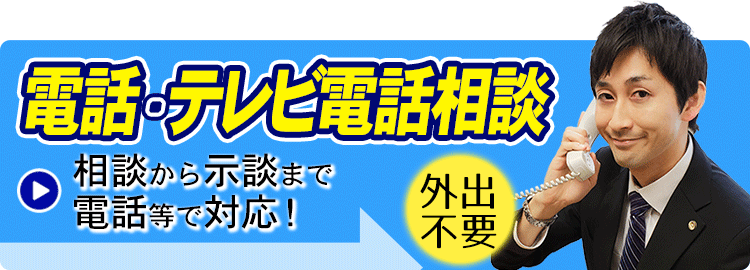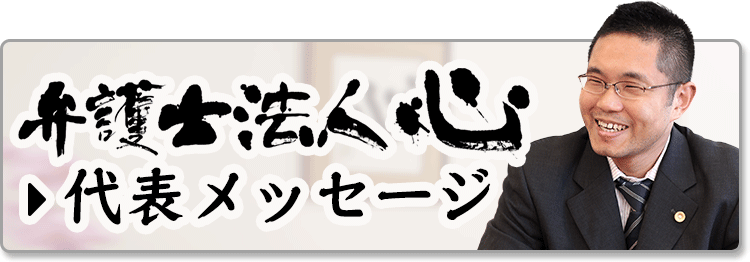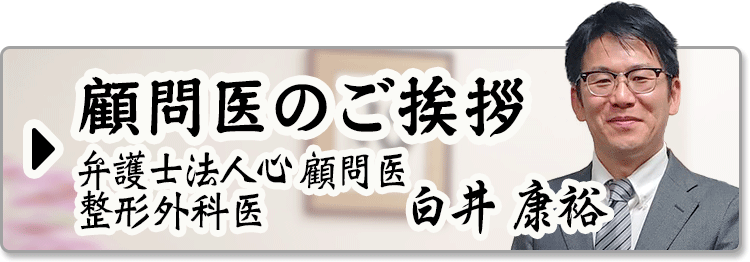後遺障害逸失利益の計算方法
1 交通事故による後遺障害逸失利益
交通事故による怪我について後遺障害の等級認定がされた場合、相手方に対して後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益は、もし交通事故に遭わず後遺障害が残らなければ、将来得ることができたであろう利益をいいます。
ここでは、後遺障害逸失利益の計算方法についてご紹介します。
2 逸失利益はどのように計算するのか
後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」という形で計算されます。
⑴ 基礎収入
基礎収入は、原則として事故前の現実の収入(年収)を基礎とします。
給与所得者の場合、源泉徴収票や支払調書などによってその金額を立証します。
個人事業主の場合、事故前年の確定申告所得額等によって収入を立証します。
主婦の場合、賃金センサスという労働者の平均賃金の統計を基礎に算定される傾向にあります。
⑵ 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害によって将来の仕事等への支障が生じる割合のことをいいます。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級によって変わり、例えば8級(脊柱の運動障害等)の場合45%、12級(鎖骨・肋骨等の変形、外貌醜状等)の場合14%、14級(局部の神経症状等)の場合5%とされています。
もっとも、被害者の職業、年齢、後遺症の部位、程度等を総合的に見て判断されます。
⑶ 中間利息控除係数
後遺障害逸失利益は将来得ることができたであろう収入について、事前に支払われるものですので、中間利息が控除されます。
そして、中間利息の控除は、労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数を乗じることによって計算します。
労働能力喪失期間は、症状固定から就労可能年齢(67歳とされています)までの年数か、平均余命の2分の1のどちらか短いほうで計算されます。
もっとも、むちうち症の場合、12級で10年程度、14級で5年程度に制限される場合もあります。
中間利息係数は、ライプニッツ係数とホフマン係数という大きく分けて二つの考え方がありますが、一般的にライプニッツ係数を用いることが傾向としては多くみられます。
3 逸失利益に関するお悩みは弁護士へ
以上、後遺障害逸失利益の基本的な考え方をご紹介いたしました。
しかし、現実にはこのような基本的な考え方では十分に損害を反映しきれない場合もあり得ます。
自分の後遺障害逸失利益はいくらくらいになるのか知りたい、相手方から提示されている金額が妥当なのか疑問に思っているという方は、交通事故を得意とする弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
当法人は、交通事故チームを作り、多数の交通事故案件を取り扱っております。
弁護士法人心 松阪法律事務所は、松阪駅1分というアクセスのよい場所にあり、周辺地域からもご相談にお越しいただいています。
交通事故でお悩みの際は、どうぞ当法人にお問い合わせください。
後遺障害の認定がされないときはどうすればよいか 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ